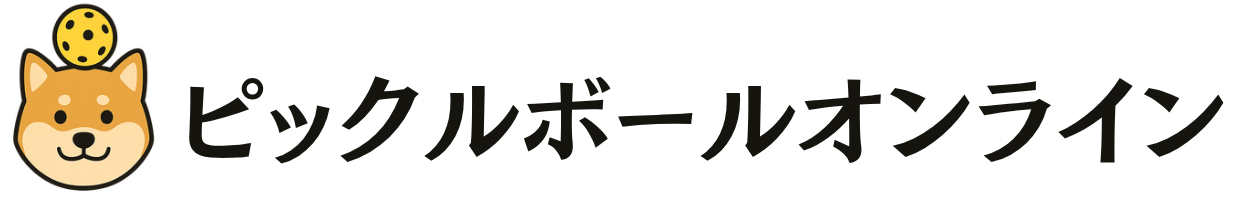国際ピックルボール連盟(GPF)とは?
国際ピックルボール連盟(GPF:Global Pickleball Federation)は、ピックルボール競技の国際的な統括団体です。

2023年11月にアメリカのUSAピックルボール(米国協会)を含む約28か国の国内連盟が結集して、GPFは設立されました。
ピックルボール界には複数の国際団体が存在していましたが、GPFは「ひとつの国際連盟」として競技ルールや運営を統一し、スポーツの健全な発展を図ることを目的としています。



非営利組織であるGPFのミッションは、ピックルボールを草の根からプロレベルまで国際的に発展・普及させることであり、「誰もが一生楽しめるスポーツ」として世界中での定着を目指しています。


GPFは設立以来急速に加盟国を増やしており、現在は北米・中南米、欧州、アジア、アフリカ、オセアニアの各地域から70か国以上が加盟しています。



これは世界のピックルボール競技人口の約95%をカバーする規模で、文字通りピックルボール界の「ワンボイス(一つの声)」となるべく活動しています。


具体的な活動内容としては、国際ルールの統一(標準化された公式ルールブックの策定)、各国連盟への技術支援やガイドライン共有、国際大会の開催支援などが挙げられます。
例えばGPFは加盟各国向けにコーチ育成プログラムを開始したり、競技用具の無償提供制度(メンバーキット助成プログラム)を立ち上げたりするなど、加盟国の競技環境整備をバックアップしています。
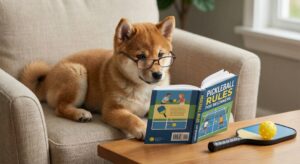
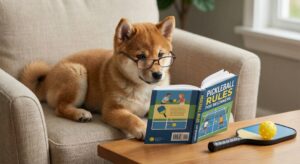
さらに世界共通のレーティングシステム導入にも踏み切り、2025年には国際ピックルボールの公式レーティングとしてDUPR(Dynamic Universal Pickleball Rating)を採用しました。



これにより世界中どこでも同じ基準で実力を評価できるようになり、競技の公平性と一体感が高まると期待されています✨️






国際ピックルボール連盟(GPF)の運営者
GPFの運営体制は、各国・各大陸の代表が結集するグローバルなボード(理事会)によって構成されています。
レガラード氏はメキシコ国内でピックルボールの普及に尽力してきた人物であり、USAピックルボールの地域ディレクターなども歴任した経歴を持つ熱心な競技推進者です。



GPF設立の発案自体は、カナダとオーストラリアの国内連盟が中心となって進められました。
国際舞台で統一された組織が必要だと感じた各国有志がタスクフォースを組み、十分な準備期間を経てGPFの創設に漕ぎ着けた経緯があります。
理事会には世界各地からピックルボール界の草分け的リーダーが名を連ねています。
例えば、オーストラリア、ガーナ、アイルランド、メキシコ、ポーランド、フィリピン、アメリカ合衆国など、それぞれの国でピックルボールをゼロから広め上げてきた創始者たちがGPFのボードメンバーとして参画しています。



こうした各国のパイオニアが力を合わせていることもあり、GPFの運営には多様な視点と豊富な経験が活かされています。
理事会は地域代表(各大陸連盟の代表)と有識者からなる枠組みで編成されており、アメリカ(USA Pickleball)やカナダからもそれぞれ2名ずつ役員が参加するなど、主要ピックルボール先進国が中心的な役割を担いながら全世界的な合議体制をとっています。
このようにGPFは民主的で包括的なガバナンスを採用しており、透明性や公平性の点でIOC(国際オリンピック委員会)の求める基準も満たす体制を整えているとされています。




国際ピックルボール連盟(GPF)とオリンピックの関係
GPFが掲げる最大の目標の一つが、ピックルボールをオリンピック競技にまで昇格させることです。
実際、GPF発足時から「IOCに国際競技連盟として正式承認されること」が優先課題に挙げられており、2025年にはIOCへの申請手続きを公式に開始しています。



この発表により、ピックルボール界は「いよいよ夢が現実に動き出した」として大きな注目を集めています。
GPFによるIOC公認への取り組みは着実に前進しており、申請後は世界アンチドーピング機構(WADA)のコード遵守やスポーツ仲裁裁判所(CAS)への認可、さらに各国への競技普及状況の報告など、IOC基準を満たすための詳細なプロセスが進められている段階です。
オリンピック正式種目になるためには乗り越えるべきハードルも多々あります。
まず競技人口と普及地域の要件として、「男性は75か国・4大陸以上、女性は40か国・3大陸以上でプレーされていること」が条件となります。
実際、GPFおよび協力関係にある他団体の合計加盟国数は2025年時点で既に75か国以上に達しており、世界的な普及度では必要ラインに近づきつつあります。
JPA(日本ピックルボール協会)も2024年にGPFに加盟済み


また、競技のルール統一や国際大会の開催実績も鍵となります。
GPFは前述のとおり国際ルールブックを整備済みであり、各地で地域別選手権やワールドカップ的な大会を開催する計画も進行中です。



例えば今後はGPF主催による公式の世界選手権や大陸選手権が開催され、各国代表がしのぎを削る場が設けられる見通しです。



さらにドーピング防止規定の導入や試合運営の公平性確保(審判員の養成や不正防止策)も急ピッチで進められており、GPFは「ピックルボール界全体の近代化」を牽引する存在となっています。


こうしたGPFの尽力により、ピックルボールのオリンピック採用の可能性も以前より現実味を帯びてきました。



現在のところ、最も有力なシナリオは2032年のブリスベン大会だと言われています。
2028年のロサンゼルス大会はすでに追加種目が確定しており時間的に間に合わないため、開催国が新競技を提案できる2032年豪州ブリスベン五輪で採用を狙うのが現実的なラインです。
オーストラリアでは国内でピックルボール人気が高まっていることも追い風で、地元オリンピック委員会の後押し次第では正式種目または公開種目として初採用される可能性が十分にあります。



実際、GPFも最終目標を「2032年ブリスベン大会でピックルボールを五輪競技にすること」と定めており、IOC承認獲得後のブリスベン大会種目入りを見据えて準備を進めています。
2025年6月には競合していた他の国際団体(IPFとWPF)が合併に合意し、GPFとの統合も模索され始めるなど、「ワンボイス体制」への前進も見られます。


国際連盟が一本化され競技団体間の政治的な争いが解消されれば、IOCにとってもピックルボールを承認しやすくなると期待されています。



専門家の中には「2032年採用の可能性は五分五分程度だが、2036年には70%以上に高まるだろう」といった予測をする声もあります。
いずれにせよ、GPFが中心となって各方面へ働きかけを続けることで、ピックルボールが五輪の舞台に立つ日も決して夢物語ではなくなってきています。
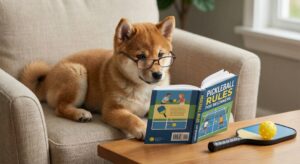
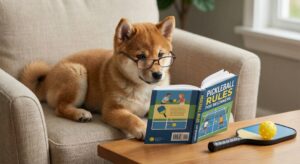


最後に
GPFの登場によって、世界のピックルボール界はこれまで以上に一体感と将来へのビジョンを持つようになりました。
わずか数年前までは各国・地域でバラバラに発展していたこの新興スポーツも、今やGPFという大きな枠組みによって一つに纏まりつつあります。



国際連盟が協調してルール作りや大会運営を行うことで、プレーヤーやファンは世界中どこにいても同じピックルボールを楽しめるようになります💕
GPFは「ピックルボールをバックヤード(自宅裏庭やジムの遊び)からオリンピックの扉口まで連れて行く」という大胆なビジョンを掲げています。
実際にIOCへの正式な申請も行い、今後は加盟国100か国に迫る勢いで仲間を増やしながら、オリンピック競技化への道を着実に歩んでいます。



GPFのリーダーシップのもと、この先ますます各国の競技レベル向上や国際大会の充実が図られていくはずです✨️